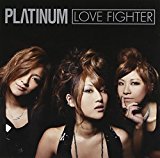音楽業界はほぼ Musicman-NET にしか求人出さない上に書類は「郵送のみ」だし、その書類も作文とか提出させるし、書類選考に最大一ヶ月ほどかかるとかいうし、ハイスペックな人を求める割には月18万とかの有期雇用だったりするし、面接は三回あったりするしとかいろいろすごい世界やなぁとかいつ見ても思います。
かつて音楽業界の片隅に居た頃にレコード会社の A&R の人たちといろいろ話す機会があったりしたけど、今思い出すとやってる仕事としてメディアリレーションなんかは企業広報と共通する部分もあったなぁと。
だから PR に必要なマインドとか思考法とかは業界共通なところもあると思うけど、音楽業界のあの内輪感・閉鎖感だと普通に事業会社で広報やってた人材とか入ってきづらいし、「音楽の売り方」を健全に議論したり考えていけるんかなーってことが心配になってきます。という話です。
中小レーベル、ブレイク前アーティストは「普通」を排除しないとほぼ売れない時代
実際に、最近だと音楽業界の PR も随分変わってきています。
まずはバンド名や歌詞やボーカルの声質やメンバーの見た目や経歴などに何かしら変なところいれて PR して、大きい舞台に立ってから小手先の個性を捨ててまっとうにロックをやりましょうみたいな売り方、圧倒的に正しいんだがそれもはや「音楽業界総V系化」みたいな話では
? H “araya” Takahashi (@51__araya) 2017年2月22日
僕は「V系化」という言葉を使っています。
「曲名とバンド名、どっちがどっちかわからん」「メンバーがとにかく○○(かわいい、オシャレ、かっこいい、おもしろいなど外見の形容詞)」「声がすごい特徴的で、一度聴いたら忘れられない」「Twitter が面白い」みたいに、音楽性より先に他の要素に言及されるアーティストがやたら増えました。
固定ファンがたくさんついたら宣伝用のフックを捨ててストレートにやり始めて、音楽メディアに「音楽にとことん真摯に向き合った姿勢が伝わってくる今作では、ロックバンドとして階段を一段上がったと思う」みたいに書いてもらうんでしょうね。まぁ否定はしないけど、V系好きって言っていろいろ言われてきた人間からすると複雑なものはある。
たとえば、最近バズった「嘘とカメレオン」とかは新人バンド PR の典型例。
ボーカルが女なのにそれより目がいくところがある最強のバンド発見した
? しずき (@Shiz_Ogu) 2017年2月19日
サウンド好きすぎる pic.twitter.com/bajdYSIKa9
Twitter で約 20,000 RT され、YouTube でも 35 万再生を記録しています(2017年3月頭時点)。
[[MORE]]
バズマーケティングは単に一過性の盛り上がりで終わってしまう事案もたくさんあるので、CD のセールスやライブ動員につながるかどうかはまた別の問題なんですが、インディーズでもそこまで動員できてない新人バンドが仕掛けた PR としては大成功じゃないかなぁと。
音楽の宣伝でも、大手レーベルであればまだ、大金を突っ込んで大型タイアップをつけたり CM を流しまくったりというゴリ押し施策をやって、ある程度のセールスを記録する → 「デビュー作がいきなりこれだけの売上を記録!」と実績を PR してさらに押す──という黄金パターンができます。
中小レーベルはそもそも物量作戦ができませんし、知恵を絞って露出を増やしていく努力が宣伝担当者に求められています。旧来の業界構造を覆すサービスをつくりたいベンチャー企業とかと似てますね。
ベンチャーなんで金もなければ人もなくて、基本的には何もないんで、あらゆることで全て負けているんですね。なので、とにかく平均的なこと、常識的なことを普通にやったら、ひとつたりとも良いことはないんで、とりあえず選択肢から平均的なこと、中央値っていうのを除外すると。
普通に頑張ると普通に負けるだけだから。 自動的に平均的なことを除外するということを早めにちゃんと意識して、自然にできるようになると良いかなというふうに思います。
これすごい大事な発言だと思うので、額に入れて飾っておきたい。
情報を届けること自体は低コストでも可能になったが「音を届ける」ことは非常に難しい、スマホ時代の広報
ただ、大手が得意な物量作戦自体も投資対効果は下降してるので、めっちゃ宣伝費かけたけど普通にフェードアウトしていったというアーティストもいます。成功例だと某家入さんとかで、失敗例だと某妖精アイドルグループとか CA 風アイドルグループとかですかね。古くは「テンションアガルネク~?( ? )?」「ダサパラ」など一部の音楽ファンの中で数々の流行語を生み出した GIRL NEXT DOOR とかありましたね(鈴木大輔ファンなので楽曲はいいと言っておきます。Orion とか Sirent Scream とか(ていうか鈴木大輔さんは後藤真希の華詩とかなんかこう地味なところに名曲バンバン提供しまくっててもっと評価されるべき))。
未だにテレビの影響力は圧倒的ではありますが、これには「セグメントによっては」という注釈がつきます。従来はテレビで PR できていたユーザーの一部がマスメディアから離れ、インターネットの世界で独自コミュニティを作り始めました。
また、インターネットのモバイル化も進んでいます。PCでじっくりネットを見る人が減り、スマホで隙間時間に見る人が増えました。移動中だったり学校だったりすると、音はオフにしてあります。イヤホンを常備してる人は少ないでしょう。
ソーシャルの時代、大量&瞬間消費の時代で、プロアマ問わず作曲家が一番苦労するようになったよなぁ 映像はまだ自動再生で2秒くらいは強制的に見せられるけど、音楽はそもそも端末のボリューム切られてること多いし、PR 施策で使っても効果が出づらいから今後地位が上がる見込みもない
? H “araya” Takahashi (@51__araya) 2016年12月17日
費用をかけなくても頭を使えば、情報を届けること自体はなんとかできます。しかし、ネットサーフィンしているスマホユーザーに「音を聴いてもらう」ことは非常に難しい時代ですので、やっぱりしばらくは “V系” 的な PR 施策で、まずスマホの音量を上げてもらう(音に興味を持ってもらう)という流れになるのではないでしょうか。
そういう意味では音楽の宣伝と最も相性いいのは「映像」なので、SNS でバズらせる動画マーケティング的な PR は今後どんどん予算は取られる(そして死屍累々になっていく)のではないかと。
とはいえ「なぜか売れた」「なぜか売れなかった」は存在しない健全さはある気がする
なんでこんな話をしたというと、メジャーデビュー前から自分がもんんんんのすごくプッシュしてたアーティストが絶賛迷走して解散、みたいな事案がたくさんあるからです。わしはこんな姿見とうなかった…。
有名どころだと school food punishment (SFP)、一応ドラマの主題歌もやってた鴉とかも非常に残念なんですが、特に「PLΛTINUM (プラチナム)」というユニットは残念でした。
3人組ガールズ J-R&B というか要するに着うた系激セツナソングみたいなジャンルなんですが、それがとにかくメロディーセンスキレッキレでアレンジも幅広い上に尖っててそこらの新人とはレベルが違うって感じやったんすよ。
シングルの前にリリースしていた 1st アルバム「LOVE FIGHTER」は、当時流行ってた着うた系激セツナソングから J-R&B っぽい曲、高速ラップとかいろいろ混ざってますが結構名盤だと思ってます。新人アーティストのメジャー1st としてはなかなかのレベル。
Dreamusic (2009-11-04)
売り上げランキング: 223,768
__
で、デビューアルバムから結構間隔を開けて満を持してリリースした1stシングル「Tears of rain」が個人的ヒット曲で、ラップ封印してまでメジャーに合わせてきたなーこれは宣伝がんばってほしいなーって思ってました。
おそらく PLΛTINUM を聞いたことがない方がほとんどだと思うので、結果はお察しです。まぁ彼女たちの場合はソナポケ師匠みたいに激セツナソング一辺倒で攻めると魅力が半減するし、かといって R&B 要素とかラップ強めのアングラ路線ではメジャーで攻められないし、みたいな葛藤が出てくるからまた別の問題もあるんですが。
ただ、PLΛTINUM が売れなかったことに関しては、宣伝の失敗というよりは企画の問題だと思っています。ファンではあるんですけど、客観的に考えて「需要がない」。つまり、この音楽を求めているユーザーがそもそも少ないと思います。 単純に10代女子に泣ける曲を提供するならギャル要素は必要ないし、ギャルに訴求するにはちょっと素直すぎる(そもそもギャル市場は小さいのでそこに絞ってメジャーで狙うには適さない)。
自分が好きなとこでいうと、鴉、小林太郎、NIKIIE も同じパターン。あと後輩がめっちゃ好きな LACCO TOWER もこのパターンで失敗するんじゃないかって話をしてます。鴉とか、ロキノン系にもV系にも好かれなさそうなどっちつかず感がすごいので詰んでるとしか(大好きなんですけどね)。
広報・PR というか Web マーケティング的に考えると、施策のポイントは「誰の、どの財布(予算)からお金をもらうか」です。PLΛTINUM などの場合、レコード会社がどんなペルソナをイメージしていたのかわかりませんが、マーケの失敗例でよくある 「そんなペルソナはいない」 事案だったのではないかと思います。
SFP の場合は、インディーズ時代の路線なら数は少なくても熱狂的に支持してくれるファンはいたものの、メジャーデビューしてもっとファン層を増やそうとして 「新規ファンとして考えていたターゲットに刺さらず、路線を変えたことで古参のファンからも見放された」という音楽業界あるある に該当すると思っています。この切替がうまくいったアーティストもいるんですけどね。ナオト・インティライミとかシドとかRADWIMPSはそんなイメージ。
売れないには売れないなりの理由があるということは常々感じています。このへんは、事業会社の広報担当者がよくある「プレスリリースつくって日経新聞のせろって言われたけど、このネタで日経本紙は無理ってわかりきっててつらい」みたいな事案と近いと思います。
ある程度の経験を積んでくると、プレスリリースが完成したときにだいたい反響が読めるわけですよ。でもそれを開発メンバーとか偉い人に言っても伝わらないんですよね。
広報的には今回は弱いネタだな~と思ってても、広報の感覚を持ってない偉い人とかには、「これ日経新聞に載せたいよね」とか「TechCrunch とか取り上げてくれないかな?」とか無茶振りされることがあります。そんなときはいくらプレスリリースの書き方とかにこだわっても、期待には応えられません。
現場と宣伝担当者で対等な関係を築けなければ音楽はなかなか売れない
自分のモットーであり、最近の広報のポイントといわれる「プレスリリースから逆算して企画を考える」ってプロセス、つまり上流工程からの広報・PR って、音楽業界やとどうなるんかなぁとか考えていた。
まぁ音楽業界はまだまだ企業体質がクラシックってのもあるので社内調整が難しそうではありますが、それ以前に根本的な問題があると思います。
じゃあ新人バンドを宣伝してくださいって状況になっても、たぶん弾はすべて揃えられた状態で、補給とかカスタマイズが許さないという状況のほうが多いんじゃないでしょうか。
PR とか マーケター的な考えでいくと「あのテレビ出させたいけど歌詞はもっとこんな感じじゃないと難しいのでは」とか色々意見を出したいわけです。
PRマン「歌詞とか曲名もうちょいいじりませんか」
かつてヒットを連発したプロデューサー様「は?なんか文句あんの?」
レコード会社の上司様「お前はまだまだ分かってないな…(呆れ)」
PRマン「こういう見た目で素材写真作りませんか」
アーティスト様「それはごもっともだけど俺の考えは違った」
PRマン「とりあえず今ある素材で売り込んでみるか…」
アーティスト様「飽きたから髪型変えました☆ 画像系全部差し替えね☆」
PRマン「あばばばば」
まぁ別に Web 制作会社でも頭固い無能なプロデューサーとか無茶ぶりしてくるクライアントはいますけどね。
広報宣伝担当者はコミュ力、折衝能力がかなり大事(他に特化していい能力もあるけど、折衝に特化したタイプの人材はかなり価値がある)っていわれますけど、対アーティスト、対レコード会社の偉い人になるとなかなか厳しいと思います。特に実績ある場合ね。
下手したら、なんかこう絶望的に何も変えられないまま最下流でメディアへのテレアポとかだけさせられそうなレイバーが求められてるかもしれない。片隅にしかいなかったけど音楽業界こわい。
とはいえレコード会社の社員さんって週休0.5日くらいで、最下流に落ちてくるタスクさばくだけでいっぱいいっぱいみたいなスケジュールだと思うし、上層部にかなりの切れ者がいないと、現場から変えていくってのはなかなか難しいのかもしれないなぁ。そもそも業界内移籍ばっかだから会社に知見貯まらなさそうだし。
結局何を考えるにしても「音楽業界の闇は深い」で締められてしまうのがマジで闇の部分だと思う。いやほんまこの先どうなるんやろあの業界。
__
(本記事は2015年4月に作成したものに大幅な加筆修正を加え、2017年3月に更新しました)